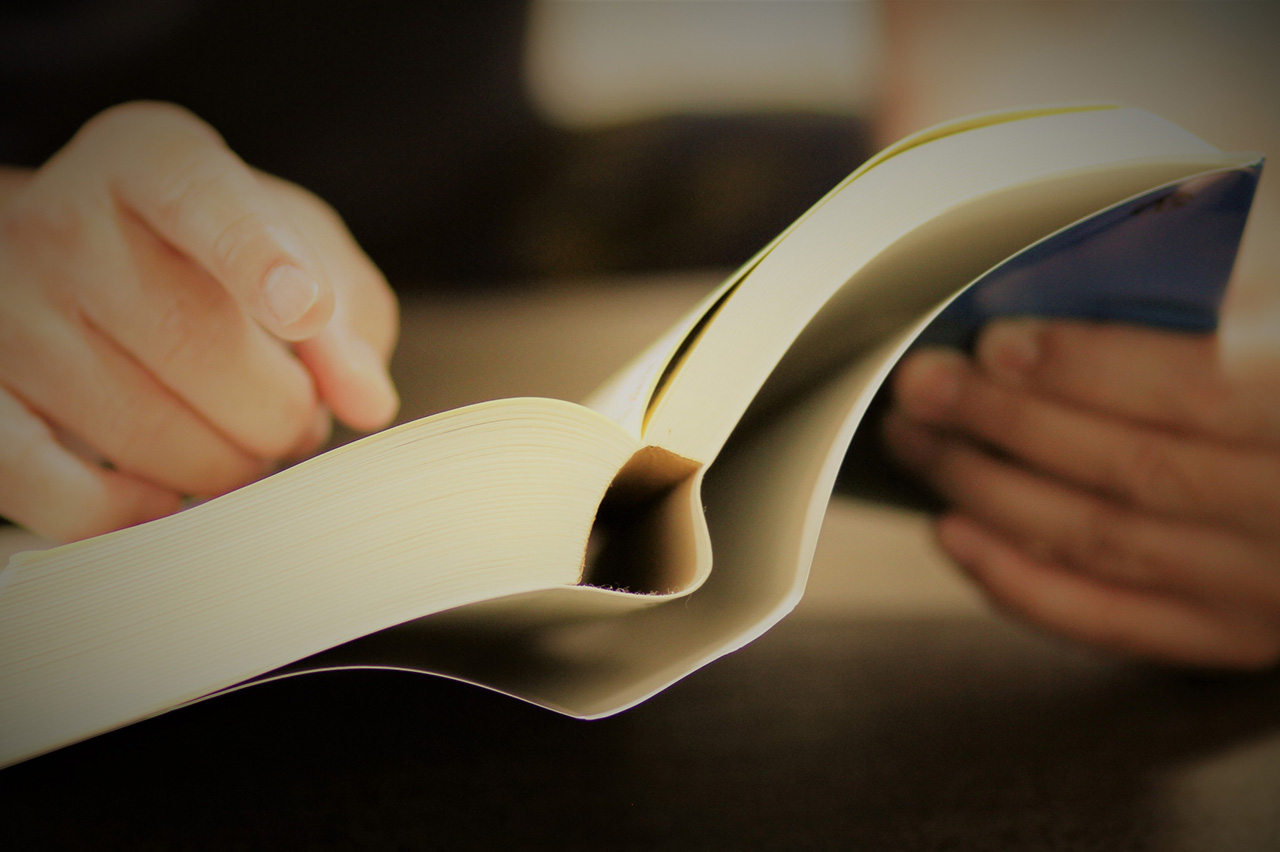
プロジェクトやプロジェクトマネジメントに携わった経験のある方なら、「PMBOK」という言葉を聞いたことがあるでしょう。PMBOKは、プロジェクトを円滑に管理し進めていくための知識をまとめた参考書のようなものです。“プロジェクトマネージャー(PM)にとってのバイブル”と言われています。
この記事では、プロジェクトマネジメントの世界標準となっている「PMBOKガイド」について詳しく解説します。これからプロジェクトに関与するという方や、プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャーとしてのキャリアプランを描いているという方は、ぜひ記事を最後までチェックし、プロジェクトマネジメントを学ぶのに必須のPMBOKガイドについて知識を深めてください。
PMBOKガイドとは?
PMBOKガイドとは、Project Management Body of Knowledgeの頭文字を略したもので、“プロジェクトマネジメントの知識体系”をまとめたガイドライン(参考文献)です。PMBOKの読み方は「ピンボック」です。
知識体系(Body of Knowledge)というと難しく感じられるかもしれません。過去の失敗や教訓から得たさまざまな手法やノウハウなどを一つにまとめ、効率よくインプットできるようにまとめた参考書をイメージしていただくといいかもしれません。
アメリカの非営利団体PMI(Project Management Institute)が、プロジェクトマネジメントの普及拡大を目的として作ったものが、PMBOKガイドです。プロジェクトマネジメントに必要なプロセスが定義されていて、プロジェクトマネジメントの世界標準となっています。
PMBOKガイドは書籍として販売されていて、PMIの会員になればHPからダウンロードして入手することも可能です。
プロジェクトマネジメントとは?
PMBOKガイドの詳細に触れる前に、一度「プロジェクトマネジメント」についておさらいしておきましょう。
プロジェクトマネジメントとは、プロジェクトを成功させる目的を達成するために、Quality(質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)のQCDや人的リソースなどのプロジェクト全体を管理することです。そしてプロジェクト全体を管理する役職に、プロジェクトマネージャー(PM)がいます。
PMやプロマネと呼ばれるプロジェクトマネージャーについては、下記の記事で詳しくご紹介していますので、そちらでご確認ください。
最新の第7版では内容が大きく変化
PMBOKはだいたい4年間隔で改定されてきており、最新版は2021年に発行された第7版です。
最新の第7版は、第6版の内容から大幅な変更があったことで、プロジェクトマネジメント界隈で大きな反響がありました。第6版から第7版での変更点については、次章で詳しく解説します。

PMBOKを学習することのメリットの一つに、世界共通で通用するプロジェクト用語を把握できるという点があります。そういった観点からもPMBOKの勉強をオススメします。
実を言いますと、私がPMBOKを真剣に勉強したのはプロジェクトマネージャーに転身してから、かなり後のことでした。それまでは、自分がエンジニアとして参加していたプロジェクトのプロマネさんのふるまいを参考にしたり、作成されていた管理資料を流用させてもらっていました。
それでもそれなりにプロジェクトはうまくこなせていたのですが、後にPMBOKを勉強し、先輩プロマネの皆様がPMBOKに従ってプロジェクト管理をしていたということがわかりました。PMBOKを学んだことで、お客様ともスムーズにプロジェクト管理の会話ができていたのだと思います。
PMBOK第7版の更新内容
PMBOKガイド第7版で、第6版から大幅な変更があったことは前章でお伝えしました。分量が800ページ弱から400ページ弱へ減ったことだけでも大きな変化があったことはわかりますが、具体的に第7版の更新内容をお伝えしていきましょう。
第6版までは、「ウォーターフォール型」や「アジャイル型」といったシステム開発手法に対するプロジェクト管理の具体的なプロセスを重視した構成になっていました。しかし、第7版ではプロジェクトに関わる人たちが、どのような姿勢でプロジェクトに臨むかという原則的なものを定義することになりました。
この記事では、更新内容の中から「原理・原則の規定」、「プロジェクトパフォーマンス領域」、「テーラリングの重要性」について、より具体的に解説します。
原理・原則の規定
PMBOKガイド第7版では、プロセスベースから「原理・原則」ベースの記載へと変更になりました。(厳密にはPMBOKガイドの中に書いてあるわけではなく、「プロジェクトマネジメント標準」という別紙に書かれているものの変更になります)
「5つのプロセス」(詳細は後述)が「12の原理・原則」に置き換わっていて、プロジェクトマネジメントの標準が大きく変化しています。原理・原則とは、“プロジェクトに関係する人への振る舞いの指針(ガイド)のこと”で、“規範ではない”と記されています。
12の原理・原則は以下のような内容となっています。
PMBOKガイド第7版「12の原理・原則」
- 勤勉で、敬意を払い、面倒見の良いスチュワードである
- 共同的なプロジェクト・チーム環境を構築する
- ステークホルダーと効果的に関わる
- 勝ちに焦点を当てる
- システムの相互作用を認識し、評価し、対応する
- リーダーシップを示す
- 状況に基づいてテーラリングする
- プロセスと成果物に品質を組み込む
- 複雑さに対処する
- リスク対応を最適化する
- 適応力と回復力を持つ
- 想定した将来の状態を達成するために変革できるようにする
プロジェクトマネジメントがこれまでよりも急速に進化しているため、“これまでのプロセスベースの指向でのガイドでは、全貌を示すための方法として維持することが難しい”という理由から、変更になったようです。原理・原則の内容は、広く一般的に普及している内容であることから、整合を維持できる方法は多くあるとPMBOKガイド第7版に書かれています。
プロジェクト・パフォーマンス領域
第6版にあった「10の知識エリア」(詳細は後述)は、別のガイドとして発刊されます。第7版では「8つのパフォーマンス領域」に変更されています。
パフォーマンス領域とは、プロジェクトの成果を効果的に提供するために欠かせない活動を8つのグループにまとめたものです。
8つのパフォーマンス領域の構成は、以下のようになっています。
PMBOKガイド第7版「8つのパフォーマンス領域」
- ステークホルダー
- チーム
- 開発アプローチとライフサイクル
- 計画
- プロジェクト作業
- デリバリー
- 測定
- 不確かさ
各パフォーマンス領域は原理・原則に基づいて作業を行うとされており、ほかのパフォーマンス領域と相互に依存していています。いずれの領域にも「ほかのパフォーマンス領域との相互作用」として、どのように関わるかがまとめられています。
また、パフォーマンス領域には決まった重み付けや順序はなく、各パフォーマンス領域の具体的な活動は組織、プロジェクト、成果物、プロジェクト・チーム、ステークホルダー、およびそのほかの要素の状況によって決まるとされています。
テーラリングの重要性
PMBOKガイド第7版には、新たに「テーラリング」専用の章が設けられました。これも第6版から大きく変わった点の一つです。
テーラリング(tailoring)とは「仕立てる・あつらえる」という意味で、各個人や環境、条件など、それぞれに合った形にパーソナライズする、カスタマイズするということと捉えていただくと、分かりやすいかもしれません。
プロジェクト・パフォーマンス領域では、結果のチェック項目にテーラリングが含まれている要素もあり、PMBOKガイド第7版には次のように記載されています。
“テーラリングとは、プロジェクトマネジメントのアプローチ、ガバナンス、プロセスが、特定の環境および目前のタスクに、より適合するように、それらを慎重に適応させることである”
つまり、PMBOKに書かれていることをもれなくすべて対応する、ということではなく、各プロジェクトに応じて必要な対応をピックアップして行っていくことが大切だということになります。
第6版までのPMBOKを勉強された方は、第7版の内容を見て正直困惑されたのではないでしょうか。かく言う私も驚きました。
第6版はプロジェクトを進めるための「ハウツー」が記載されていたのに対し、第7版はプロジェクトを行うにあたっての心構えをまとめた「バイブル」であると言えるかもしれません。
第6版でも記載はあったのですが、今回「テーラリングの重要性」についても大きく取り上げられることになりました。これはそれぞれのプロジェクトに合わせて柔軟に必要な対応をしていくことが大事である、という強いメッセージだと考えます。
なお、これまでPMBOKはプロマネが読むべき知識体系でしたが、第7版からはプロジェクトに関わるすべてのステークホルダーが参考にすべき対象となっています。
第6版以前でまとめられていたPMBOKの内容
さて、第7版では記載されていなかったものの、第6版以前に記載されていた内容は、今後のプロジェクト管理においてもプロマネが参考とすべき内容であり“変わらず重要”です。
この章では、第6版以前にまとめられていた「PMBOKの『10の知識エリア』」と、「PMBOKの『5つのプロセス』」について解説します。
プロジェクトマネジメントに大切な「10の知識エリア」とは?
PMBOKには、プロジェクトマネジメントに大切な“知識エリア”と呼ばれるものがあります。そのエリアを、10種類に分割したものが下記の「10の知識エリア」です。
PMBOKの「10の知識エリア」
- 統合マネジメント
- スコープマネジメント
- スケジュールマネジメント
- コストマネジメント
- 品質マネジメント
- 資源マネジメント
- コミュニケーションマネジメント
- リスクマネジメント
- 調達マネジメント
- ステークホルダーマネジメント
先にお伝えした通り、この10の知識エリアは、第7版では「8つのパフォーマンス領域」に置き換わっています。第7版での記載はなくなったものの、10の知識エリアはプロジェクトマネジメントにおいて変わらず重要なものです。10の知識エリアの詳細については以下の記事で詳しく紹介しています。
プロジェクトマネジメントの重要な考え方「5つのプロセス」
10の知識エリアとともに第6版までにまとめられていた重要な内容が、「5つのプロセス」です。第6版では、プロジェクト開始から終了までの流れを、下記の5つに分類しています。
PMBOKの「5つのプロセス」
- 立ち上げプロセス
- 計画プロセス
- 実行プロセス
- 監視・コントロールプロセス
- 終結・プロセス
第7版では、「12の原理・原則」に変わりましたが、プロジェクトをフェーズでとらえ、管理していくためには、「5つのプロセス」は変わらず重要な考え方と言えます。
5つのプロセスの詳細については以下の記事で詳しく紹介しています。
PMBOK第7版が大幅に改定されたからと言って、第6版までの内容が陳腐化したわけではありません。PMBOK第6版は十分参考になります。なお、これらの内容は「プロセス群実務ガイド」という別のガイドで、その内容を確認することができます。
これからPMBOKを勉強される方は、第7版だけを勉強すると理念は理解できても具体的なハウツーについては習得できません。第6版までに記載された知識エリアやプロセスを体系立てて理解するには別途勉強されることを強くオススメします。
プロジェクトマネジメントに欠かせない「PMBOK」
この記事では、プロジェクトマネジメントに欠かせない、プロジェクトマネージャーにとってのバイブルと言える「PMBOK」について、最新の第7版と第6版までの違いについて解説しました。PM、プロマネとしてのキャリアプランを描いている方は、PMBOKでプロジェクトマネジメントのことを学び、PMIが実施しているプロジェクトマネジメントの資格「PMP資格」の受験を検討されてはいかがでしょうか?
タカハマプロジェクトでは、「ビギナー向け」「PM経験者向け」にトレーニングコースをご用意しております。プロジェクトマネジメントの基本を知りたい方、プロジェクトマネージャーとしてスキルアップしたいという方は、下記のボタンよりお気軽にお問合せください。
